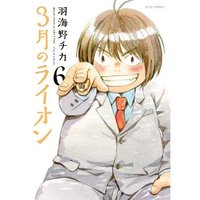2011年04月22日
上関原発予定地取材記。:4
どうにもこうにも、深く考えれば考えるほど、答えのでない難しい問題です。
※今回、ものすごく長文になることは、ごめんなさい、あらかじめ謝っておきますm(_ _)m
とりあえず、これまでの内容について、簡単にまとめてみます。
Ustreamやツイッターで上関原発についての話題をよく見ていました。
それは、一般的なニュースにはならないことでした。
けれど、見ていると「祝島住人+全国の反原発派vs中国電力」の構図で、当事者であるはずの上関町の住人がまったくといっていいほど表に出てきませんでした。
いったい、どういうことなのだろう?そんな違和感を確かめるべく、現地へ行って、見たことが契機でした。
やっぱり、百聞は一見に如かず、でした。

上関原発からは、東山口の変電所を経由して、そこから主に広島、岡山、関西方面へ電力が送られるということです。
まず、これは現地だけの問題と言うよりも、都市部と過疎化の進む非都市部との間にある、一種の従属・被従属といった「南北問題」ともいえる構造があるということです。
さらに見てみると、過疎・限界集落の問題が、原発推進の背景の大きな「構造」になっていることがわかりました。
基本的な福祉や医療が行き届かず、産業もない状態。
それでも、その土地で生きていくための手段が他に見あたらないということがあるのです。
ツイッターでも話題になった、『福島には原発が必要だった』というブログ記事があります。
「必要だ」ではなく「必要だった」です。
とても正直に、現地の状況を書いてくださった素晴らしい文章だと思います。
町の財政が非常に悪化していたこと、そして、説明会などでは「原発は絶対に安全」ということが繰り返し強調して説明されてきたこと……財政難の過疎地での「藁にもすがりたい」という気持ちは、原発受け入れ地だけの問題ではありません。
単に一つの原発や、その受け入れ地域を叩くのではなく、そういった過疎と財政難につけこまれる「構造」自体をなんとかしないと、原発問題の解決はないと考えます。
そして、現状ではやはり上関町も老人福祉など、「地元で生きるための最低限のラインを確保するため」原発の交付金を使用しています。
本来憲法で保障されているはずの「最低限の文化的生活」が、こういった過疎地では保障されていないのです。
それを補うために「原発受け入れ」という選択肢を選んだ上関住民を責めることはできないのではないでしょうか?
もちろん、これは原発が賛美されるようなものではなく、本来行政や福祉が行うべき事が行われていないことに問題の本質があります。
そして、福島原発の例をみてわかる通り、事故がおきたときには、とりかえしのつかないことになりますし、一番被曝して被害を被るのも、また受け入れ地の住人でもあるのです。
もちろん、個人的には原発はないほうがいいと考えます。
ただ、いわゆる「反対派」が述べる言説にある、『原発が嫌なら声をあげて廃炉に追い込む行動をしなければ「容認」と同じ』という言葉や、「受け入れ」を表明した地域を、交付金に目がくらんだ「金の亡者」だとか、地球を滅ぼす「加害者」だとかいうのは、全くの筋違いなのではないでしょうか?
ここで、いまこの文章を書いている自分自身が掲げたい大前提を、声を大にして(太文字にして)表明したいと思います。
【いかなる状況であれ、立場の弱いものたちの生活や人権はなんとしても守られなくてはならない】
これだけは、外せない“原点”です。
仮に考えが違う相手でも、その相手の人権を無視するような言説や行動、さらには差別はあってはならない。
他に、原発の問題を考えたときに、もう一つ難しい問題があります。
それは、日本の産業をぎりぎりのところで下支えしている町工場の人達の生活です。
さきほど、上関からの電気は、現地住民が使うのではなく、広島や関西の都市部に送られるものだと書きました。
その都市部の中にも“格差”が存在します。
とくに、電気代が高くなると操業がなりゆかなくなる町工場で働いている人達の生活の問題があります。
現状では、代替エネルギーはまだコストがかかりすぎるのです。
ぎりぎりで操業している工場のひとたちに対して「電気代が高くなっても、安全のためには我慢しろ」では、倒産や自殺が相次ぐことになってしまいます。
また、福島や上関町などの原発推進地の人達の人権について、非常に気がかりなことがあります。
強硬的に「反原発」を唱える人ほど、原発推進地の人達に対して、
「現状がイヤなら、その地からでていけ」
「金貰っているんだから、被災しても文句言うな」
という言説を多く見かけます。
それは違う、差別になってしまうと叫びたいです。
現地を出て行くことができるひとたちは、そういう土地ではとっくに現地を出ています。
例えば上関町でも、もともとの過疎化に加え、ここ最近になって急激に過疎化に拍車がかかっていることなどに顕著に現れています。
「それでも」、様々な事情(引っ越し費用、人間関係、土地への愛着等)から、出て行くことができない人達がいるのです。
その地で一生を過ごさねばならない人達がいるのです。
彼らを「棄民」してはならないと思うのです。
ただ、そうはいっても、原発には安全性の問題をはじめ、様々な問題が山積みしていることも事実です。
それに、沖縄などもそうなのですが、交付金に頼っていると自立が阻害されたり、交付金を使って必要のないハコモノを建設したり、意味無く使わない道路の工事や埋めたてが行われて、山野や海がめちゃくちゃになることも見てきました。
上関町でも、現在までは福祉を中心に交付金が使用されてきましたが、ハコモノを2施設建設するという計画があるそうです。
こういったハコモノで潤ったという話は全国的に聞きません。
作ったはいいものの、その後の管理運営費に四苦八苦する話もよく聞きます。
また、原発関連で生じる雇用は一時的なものです。
建設の利益は、都市部の大手建設会社に回ります。
完成後は、地元におりてくる利益はほとんどないことが常態です。
そして、やはり原発の話で避けて通ることができないのが、事故や被災の可能性です。
被災で直接的な被害を被るのは、都市部の人達ではありません。
原発を受け入れた、過疎・限界集落の現地の人達なのです。
「原発は安全」という神話がありましたが、もとから政府は、「被災可能性がある」ことがわかっているからこそ、交付金を出すのです。
本当に安全だったら、公共の福祉のために用いられる施設の建設予定地の人達に、お金なんて一円も出しません。
その欺瞞は理解していないと、後々大変なことになります。
さて、繰り返しになりますが、そこには、福祉や人権の問題といった「構造」がありました。
人権や生活を守りつつ、「構造」を打破する道を探る必要があります。
期待された方には、謝るしかないのですが、解決策は提示できません。
それでも、「少しはなんとかできるかも」「マシにできるかも」な部分を増やすための可能性の話をしたいと思います。
もしかしたら、ここで述べるものは、実行不可能なものや現地に合わないものもあるかもしれません。
実際、いろんな制度を調べているうちに、初めは「これは有効だろう」と思っていたものが、実際は机上の空論に終わることが見えたものがいくつもあって、頭を抱えてしまいました。
それでも、何かの叩き台になればいいなと思い、いくつか提言を挙げてみようと思います。
正直に言うと、誰もが幸せになる道はありませんが、「誰もがちょっとずつ不幸を分け合う」ことができれば、それが最適解なのかもしれないとも思います。
○都市部の問題について:
原発は、いわば「都市部の生活のためのエゴ」でもあります。
それは、福島で作られた電気は東京へ送られること、上関で作られた電気は広島や関西の都市部へ送られることからも明確です。
ありきたりな言葉になりますが、都市部の生活スタイルの変化は必要だと思います。
過疎地の人達を踏みつけにして成り立つような暮らしをこのまま続けていいのか、という問いになります。
また、現在は東日本と西日本では使用電力は周波数が違います。
だから、例えば西日本で余っている電気を東日本に送ることが不可能な事態が生じてしまいました。
この周波数の違う電力を、相互換算できるようにすることは重要な課題です。
この件については、調べてみると、電力融通を、5年以上かけて現状の数倍の300万~500万キロワットに増やす方針だそうです。(2011年4月14日、朝日新聞より)
また、現在では、作られた電力をプール(保存)する施設がとても限られるそうです。
とくに、原子力でつくられた電力は時間を選ばないため、夜間は余剰電力が発生するのに、その余剰電力を昼間の電力に生かせないという現象が発生しています。
そうした電力をまず備蓄できるようにしていくこと。
そうやって、現行のインフラを固め、都市部内での格差がある場所(町工場など)に必要なエネルギーが値上げせずとも行き渡るようにしたうえで、代替エネルギーが安く得られるよう、研究・開発を進めていくべきだと考えます。
実際問題、様々な代替エネルギーの可能性はでてきています。
原発が国策として最も推進されたのはもう30~40年前の話です。
パソコンや携帯電話も、この十数年で爆発的に普及し、安くなり、技術が進歩しました。
同じように、代替エネルギーも現状ではコストがかかりすぎますが、将来の可能性は大いにあると考えます。
ただ、それは一朝一夕に進められるモノではないため、まずは現状にあるものでなんとかしなければならないと考えます。
○電力会社に競争を取り入れる:
現在、電力会社には競争がありません。
それぞれの地域の電力会社(関東なら東電、中国地方は中電など)の独占体制です。
これは、さらにその上部組織の経済産業省などの政治組織の「国策」でもあります。
ここに競争を取り入れていかないことには、代替エネルギーも安くなりませんし、原発推進のために過疎地が狙われることになります。
原発受け入れ地が「受け入れ」を決めるまでには、本当にどこも様々な紆余曲折があり、苦悩があります。
地域が推進と反対に二分してしまい、もとからあった共同体が機能不全に陥ってしまうことも頻繁にあります。
立場の弱い地域は、そのように、「国策」に翻弄されてしまうのです。
そして、その多くが地域の弱みを詳細に調査したうえで行われるので、対抗することが難しいのです。
だからこそ、「国策」だけではないオルタナティブが必要だと考えます。
○「Iターン」という選択肢:
過疎地の多くは、UターンやIターンで人が来ることを積極的に受け入れようとしています。
これは、上関町も例外ではありません。
例えば、「定住促進住宅の整備(※平成21年度の資料では同年に3戸建設予定)」という制度があります。
上関町へ定住を希望されている家族や移住を考えている家族の方に対し、木造二階建・4DKの電化住宅を福浦地区に建設し、将来的には入居された方に払い下げ、定住の促進を図るというものです。
原発反対を本気で考える人達は、安全な都市部から声を出すのではなく、こういった制度を利用して、現地の人達と「共に」考えていくというのは一つの方法だと思います。
住むことで、初めて見えてくることもたくさんあります。
もっとも、この事業の元のお金が、原発の交付金から出ているのは皮肉な話ではありますが…。
あと、これはあまり勧めたくない「裏技」ですが、現地に住民票を移して3ヶ月居住すると選挙権が得られます。
現在、上関町でも原発反対派は4割ほどいます。
それと合わせると、600~700人も反対派が住めば、現状の原発に対する賛成と反対が逆転するという現象が生じます。
ただし、
・移住者は町民に受け入れられないことは覚悟した上で
・それでも対話をあきらめず、粘り強く話し合うこと
・いったん、原発「賛否」の価値観を捨てて、幅広く現地の良いところも悪いところも見ること
・選挙後も住み続け、労働力になること
・現地に貢献すること
これらは絶対条件であり、必要最低限のマナーだと考えます。
それがなければ、移住しても迷惑なだけです。
実際に、某宗教団体を母体にしたとある政党は住民票を3ヶ月移して、選挙が終わると同時に住民票を引き上げることをしているという話はよく聞きますが、それと同じ汚いやり口になってしまうということは、強調しても強調しすぎることはないでしょう。
○上関町を訪れた人は、上関町の生活も意識的に見てみる:
これだけなら、ハードルはずっと低くなると思います。
全国から、「反原発」で上関町を訪れる人はたくさんいますが、上関町の人々と交流することはおろか、彼らの生活をまったく見もしないで、騒ぐだけ騒いで帰ってしまうことは非常に残念です。
いわば、「木を見て森を見ず」な状況なわけです。
上関町の自然について書かれた、いわゆる「反原発派」によるブログはたまに見かけますが、そこに地域の人達の暮らしについて書かれた文章を見かけることは、まったくと言っていいほど皆無なのです。
どんなに豊かな自然や綺麗な海があっても、それだけでは生きていけません。
それどころか、むき出しの自然は、人間にとって大きな脅威となって襲いかかることの方が多いのです。
ともかく、現地を訪れた人達は、どういう理由で訪れたのであれ、原発だけに視野狭窄するのではなく、上関町民の生活などに関心を持って先入観をなるべく持たずに見ることをして欲しいと願います。
抽象的な「反原発」よりも、原発を必要としなくても暮らせるような、人間らしい暮らしを取りもどすことへの協力を、現地を訪れた人達には考えて欲しいと切望します。
それがなければ、「反原発」を掲げることは、ヒューマニズムにもとる、ただのクレイマーでしかないと考えます。
○過疎地に対しての支援制度を利用する:
実は過疎地には、支援制度が存在します。
それは、『過疎地自立対策特別措置法』といいます。
産業の振興、生活環境の整備、高齢者の保健及び福祉の向上及び増進、医療の確保、教育の振興、集落の整備などを支援するお金が公費ででます。
28年前に、上関に原発案が持ち上がった段階ではその制度があったかどうか、また、上関町が条件にあてはまったかどうかはわかりません。
けれども、現在の上関町はその制度で規定する「過疎地」にあてはまります。(※山口県の公式ホームページで確認済みです。)
原発の交付金があったせいかわかりませんが、上関町はまだその制度を一度も利用していないようです。
最新版の『山口県過疎地域自立促進計画について』のPDFは以下のアドレスになります。
http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a123003/kaso/hosin-keikaku/apd1_3_2011020117163804.pdf
この制度を使えば、原発の交付金ほどのお金は入らなくとも、最低限の現状維持は可能かもしれません。
ただし、山口県は過疎地が上関町に限らず非常に多い県なので、どのくらいの支援費が入るのかは未知数という問題はあります。
それでも、一考には値するのではないかと考えます。
○NPOによる、共同体生活ネットワークサービスの利用:
上関町では、商店がないことにより、生鮮食品の入手も困難な家庭が多いと聞きます。
もしかすると、生協のような宅配でのサービスもないのかもしれません。
このような分野を、なるべく費用の負担をサービス受益者に負わせずに行うNPOも存在します(もちろん、無償とはいきませんが)。
こういった、NPOを活用して地域の共同体のあり方を作り直してみるという方法も一案だと考えます。
実際、過疎地の自立支援を専門にするNPOもあります。
現在、上関町では、細々と行われている農業や漁業についても、農協や漁協がきちんと機能していないという話も聞きます。
流通ルートがないから、産業が先細るのです。
こういった、販路をNPOを通じて開拓していくことも、地域の自立に向けた取り組みとして意義のあることではないかと考えます。
○「エンパワメント」という概念:
エンパワメントとは、直訳すると「力をつける」ということですが、もっと正確にいうと「自分自身の力で問題や課題を解決していくことができる社会的技術や能力を獲得すること」になります。
援助・被援助ではない、第3の道です。
この「エンパワメント」という概念を用いた福祉問題へのアプローチでは、当事者たち自身がそのおかれた状況に気づき、問題を自覚し、自分たちの生活をコントロールしたり、改善したりする力をつけることが目指されます。
実際、この概念は社会的マイノリティや少数民族、女性、障がい者の自立に関する考え方のベースとして使われています。
力(Power)をつけること、ないし力を獲得すること。
社会的・経済的な力をもたない貧しい人々や女性など、制度化された政治的・経済的過程に参加できず、人間開発の過程から排除され、力を奪われている(Disempowered)人たちが、自らの自己決定能力といった心理的な力や、社会的・政治的・法的な力を獲得する(自己をエンパワーする=self-empowerment)こと。
1970年代半ば以降、国連や国際会議の場で、「オルタナティブな開発」が唱えられ、「開発と女性」「持続可能な開発」、等が論じられる中で、貧困からの脱出や開発途上国の女性の「基本的ニーズ」に答えるための、環境・福祉優先型開発の必要が提起されるようになりました。
そうした議論の中で強調され、広まってきたのが、「エンパワーメント」の概念です。
交付金依存の生活では、自立ができなくなります。
そこからの脱却を考えていく上で、外せない概念だと考えます。
また、この概念を実際の生活に当てはめて実践していくには、先ほど挙げたような、過疎地支援を専門にしているNPOの協力を仰ぎながら、しっかりとしたロードマップ(工程表)を作成し、住民合意の元で行われる必要があります。
○外部人材の受け入れと「山村留学」:
先に挙げた、「Iターン」の話とも絡んできますが、過疎地でのIターンや外部人材の受け入れが成功している地域があります。
例えば、島根県隠岐島の海士(あま)町。
『なぜか「勝ち組」若者が移住してくる離島 5年半で230人の新規定住者獲得~島根県・海士町』
もちろん、地域的条件が同じではないですから、そのまま取り入れられない部分は多々あるでしょう。
それでも、参考になりそうな部分も多くあります。
例えば、2010年4月からスタートした「島留学制度」。
寮費を町が全額補助する学生寮を用意して、全国から学生を募集する。特色ある教育を打ち出すため、「地域創造」と「特別進学」の2コースを新設しています。
地域創造コースは、「将来、家業を継ぎたい」「地元の町を元気にする仕事をしたい」「いつか村長になる」など、地域社会で自立・活躍できる人材育成を目指すものです。
豊かな地域資源を活かした独自のプログラムや自然体験を通じて、主体性・想像力・コミュニケーション力を磨くことを目指しています。
特別進学コースは、大手予備校がない島の生徒でも難関大学を突破できる学力をつけるためのカリキュラムを用意し、少人数の徹底指導に加えて、島外から「進学のプロ」を招いた公営塾まで設置することを売りにしています。
このようにして、外部からの若い人材の確保、そして、地元で育った人が地元で仕事を創出する『人の自給自足』の流れを作り出そうとしています。
こういった離島での、子どもたちの受け入れは沖縄県などでもよく見られます。
例えば、久高島での「山村留学」。
久高島は他の多くの離島や僻地と同じように近年人口が減少し、学校も超小規模校となっています。
しかし、過疎や小規模校と言うハンディを逆手にとって、沖縄のこのような島だからこそできる活動があるということを「活動趣旨」で述べています。
全国の不登校児童生徒や、親が養育しにくくなった子どもたちをこういった地で受け入れ育て、やがては地域に貢献する人材に育てようと、地域ぐるみ島ぐるみで取り組んでいると聞きます。
このようなことは、沖縄では鳩間島や渡嘉敷島でも行っています。
鳩間島は、ドラマ『瑠璃の島』でもその様子が有名になりました。
かつて過疎化により島の小中学校が廃校の危機に直面したことから、島の人が「里親」となって島外からの児童を里子として受け入れる「海浜留学」を実施しているのです。
このような取り組みは、上関町などの過疎地域でも行うことができるのではないでしょうか?
将来の人材育成のためにも!
以上、様々なことを述べてきましたが、簡単な解決策はありません。
だから、どうしても、歯切れの悪さ、後味の苦さは残ります。
それでも、そういった諸々を受け止めつつ「共に生きて」いくことを志向したいです。
これら過疎地の人権、生活の確保が達成できたとき、初めて大きな声で「原発は必要ない、いらない!」とやっと言えるのだと思うのです。
※今回、ものすごく長文になることは、ごめんなさい、あらかじめ謝っておきますm(_ _)m
とりあえず、これまでの内容について、簡単にまとめてみます。
Ustreamやツイッターで上関原発についての話題をよく見ていました。
それは、一般的なニュースにはならないことでした。
けれど、見ていると「祝島住人+全国の反原発派vs中国電力」の構図で、当事者であるはずの上関町の住人がまったくといっていいほど表に出てきませんでした。
いったい、どういうことなのだろう?そんな違和感を確かめるべく、現地へ行って、見たことが契機でした。
やっぱり、百聞は一見に如かず、でした。

上関原発からは、東山口の変電所を経由して、そこから主に広島、岡山、関西方面へ電力が送られるということです。
まず、これは現地だけの問題と言うよりも、都市部と過疎化の進む非都市部との間にある、一種の従属・被従属といった「南北問題」ともいえる構造があるということです。
さらに見てみると、過疎・限界集落の問題が、原発推進の背景の大きな「構造」になっていることがわかりました。
基本的な福祉や医療が行き届かず、産業もない状態。
それでも、その土地で生きていくための手段が他に見あたらないということがあるのです。
ツイッターでも話題になった、『福島には原発が必要だった』というブログ記事があります。
「必要だ」ではなく「必要だった」です。
とても正直に、現地の状況を書いてくださった素晴らしい文章だと思います。
町の財政が非常に悪化していたこと、そして、説明会などでは「原発は絶対に安全」ということが繰り返し強調して説明されてきたこと……財政難の過疎地での「藁にもすがりたい」という気持ちは、原発受け入れ地だけの問題ではありません。
単に一つの原発や、その受け入れ地域を叩くのではなく、そういった過疎と財政難につけこまれる「構造」自体をなんとかしないと、原発問題の解決はないと考えます。
そして、現状ではやはり上関町も老人福祉など、「地元で生きるための最低限のラインを確保するため」原発の交付金を使用しています。
本来憲法で保障されているはずの「最低限の文化的生活」が、こういった過疎地では保障されていないのです。
それを補うために「原発受け入れ」という選択肢を選んだ上関住民を責めることはできないのではないでしょうか?
もちろん、これは原発が賛美されるようなものではなく、本来行政や福祉が行うべき事が行われていないことに問題の本質があります。
そして、福島原発の例をみてわかる通り、事故がおきたときには、とりかえしのつかないことになりますし、一番被曝して被害を被るのも、また受け入れ地の住人でもあるのです。
もちろん、個人的には原発はないほうがいいと考えます。
ただ、いわゆる「反対派」が述べる言説にある、『原発が嫌なら声をあげて廃炉に追い込む行動をしなければ「容認」と同じ』という言葉や、「受け入れ」を表明した地域を、交付金に目がくらんだ「金の亡者」だとか、地球を滅ぼす「加害者」だとかいうのは、全くの筋違いなのではないでしょうか?
ここで、いまこの文章を書いている自分自身が掲げたい大前提を、声を大にして(太文字にして)表明したいと思います。
【いかなる状況であれ、立場の弱いものたちの生活や人権はなんとしても守られなくてはならない】
これだけは、外せない“原点”です。
仮に考えが違う相手でも、その相手の人権を無視するような言説や行動、さらには差別はあってはならない。
他に、原発の問題を考えたときに、もう一つ難しい問題があります。
それは、日本の産業をぎりぎりのところで下支えしている町工場の人達の生活です。
さきほど、上関からの電気は、現地住民が使うのではなく、広島や関西の都市部に送られるものだと書きました。
その都市部の中にも“格差”が存在します。
とくに、電気代が高くなると操業がなりゆかなくなる町工場で働いている人達の生活の問題があります。
現状では、代替エネルギーはまだコストがかかりすぎるのです。
ぎりぎりで操業している工場のひとたちに対して「電気代が高くなっても、安全のためには我慢しろ」では、倒産や自殺が相次ぐことになってしまいます。
また、福島や上関町などの原発推進地の人達の人権について、非常に気がかりなことがあります。
強硬的に「反原発」を唱える人ほど、原発推進地の人達に対して、
「現状がイヤなら、その地からでていけ」
「金貰っているんだから、被災しても文句言うな」
という言説を多く見かけます。
それは違う、差別になってしまうと叫びたいです。
現地を出て行くことができるひとたちは、そういう土地ではとっくに現地を出ています。
例えば上関町でも、もともとの過疎化に加え、ここ最近になって急激に過疎化に拍車がかかっていることなどに顕著に現れています。
「それでも」、様々な事情(引っ越し費用、人間関係、土地への愛着等)から、出て行くことができない人達がいるのです。
その地で一生を過ごさねばならない人達がいるのです。
彼らを「棄民」してはならないと思うのです。
ただ、そうはいっても、原発には安全性の問題をはじめ、様々な問題が山積みしていることも事実です。
それに、沖縄などもそうなのですが、交付金に頼っていると自立が阻害されたり、交付金を使って必要のないハコモノを建設したり、意味無く使わない道路の工事や埋めたてが行われて、山野や海がめちゃくちゃになることも見てきました。
上関町でも、現在までは福祉を中心に交付金が使用されてきましたが、ハコモノを2施設建設するという計画があるそうです。
こういったハコモノで潤ったという話は全国的に聞きません。
作ったはいいものの、その後の管理運営費に四苦八苦する話もよく聞きます。
また、原発関連で生じる雇用は一時的なものです。
建設の利益は、都市部の大手建設会社に回ります。
完成後は、地元におりてくる利益はほとんどないことが常態です。
そして、やはり原発の話で避けて通ることができないのが、事故や被災の可能性です。
被災で直接的な被害を被るのは、都市部の人達ではありません。
原発を受け入れた、過疎・限界集落の現地の人達なのです。
「原発は安全」という神話がありましたが、もとから政府は、「被災可能性がある」ことがわかっているからこそ、交付金を出すのです。
本当に安全だったら、公共の福祉のために用いられる施設の建設予定地の人達に、お金なんて一円も出しません。
その欺瞞は理解していないと、後々大変なことになります。
さて、繰り返しになりますが、そこには、福祉や人権の問題といった「構造」がありました。
人権や生活を守りつつ、「構造」を打破する道を探る必要があります。
期待された方には、謝るしかないのですが、解決策は提示できません。
それでも、「少しはなんとかできるかも」「マシにできるかも」な部分を増やすための可能性の話をしたいと思います。
もしかしたら、ここで述べるものは、実行不可能なものや現地に合わないものもあるかもしれません。
実際、いろんな制度を調べているうちに、初めは「これは有効だろう」と思っていたものが、実際は机上の空論に終わることが見えたものがいくつもあって、頭を抱えてしまいました。
それでも、何かの叩き台になればいいなと思い、いくつか提言を挙げてみようと思います。
正直に言うと、誰もが幸せになる道はありませんが、「誰もがちょっとずつ不幸を分け合う」ことができれば、それが最適解なのかもしれないとも思います。
○都市部の問題について:
原発は、いわば「都市部の生活のためのエゴ」でもあります。
それは、福島で作られた電気は東京へ送られること、上関で作られた電気は広島や関西の都市部へ送られることからも明確です。
ありきたりな言葉になりますが、都市部の生活スタイルの変化は必要だと思います。
過疎地の人達を踏みつけにして成り立つような暮らしをこのまま続けていいのか、という問いになります。
また、現在は東日本と西日本では使用電力は周波数が違います。
だから、例えば西日本で余っている電気を東日本に送ることが不可能な事態が生じてしまいました。
この周波数の違う電力を、相互換算できるようにすることは重要な課題です。
この件については、調べてみると、電力融通を、5年以上かけて現状の数倍の300万~500万キロワットに増やす方針だそうです。(2011年4月14日、朝日新聞より)
また、現在では、作られた電力をプール(保存)する施設がとても限られるそうです。
とくに、原子力でつくられた電力は時間を選ばないため、夜間は余剰電力が発生するのに、その余剰電力を昼間の電力に生かせないという現象が発生しています。
そうした電力をまず備蓄できるようにしていくこと。
そうやって、現行のインフラを固め、都市部内での格差がある場所(町工場など)に必要なエネルギーが値上げせずとも行き渡るようにしたうえで、代替エネルギーが安く得られるよう、研究・開発を進めていくべきだと考えます。
実際問題、様々な代替エネルギーの可能性はでてきています。
原発が国策として最も推進されたのはもう30~40年前の話です。
パソコンや携帯電話も、この十数年で爆発的に普及し、安くなり、技術が進歩しました。
同じように、代替エネルギーも現状ではコストがかかりすぎますが、将来の可能性は大いにあると考えます。
ただ、それは一朝一夕に進められるモノではないため、まずは現状にあるものでなんとかしなければならないと考えます。
○電力会社に競争を取り入れる:
現在、電力会社には競争がありません。
それぞれの地域の電力会社(関東なら東電、中国地方は中電など)の独占体制です。
これは、さらにその上部組織の経済産業省などの政治組織の「国策」でもあります。
ここに競争を取り入れていかないことには、代替エネルギーも安くなりませんし、原発推進のために過疎地が狙われることになります。
原発受け入れ地が「受け入れ」を決めるまでには、本当にどこも様々な紆余曲折があり、苦悩があります。
地域が推進と反対に二分してしまい、もとからあった共同体が機能不全に陥ってしまうことも頻繁にあります。
立場の弱い地域は、そのように、「国策」に翻弄されてしまうのです。
そして、その多くが地域の弱みを詳細に調査したうえで行われるので、対抗することが難しいのです。
だからこそ、「国策」だけではないオルタナティブが必要だと考えます。
○「Iターン」という選択肢:
過疎地の多くは、UターンやIターンで人が来ることを積極的に受け入れようとしています。
これは、上関町も例外ではありません。
例えば、「定住促進住宅の整備(※平成21年度の資料では同年に3戸建設予定)」という制度があります。
上関町へ定住を希望されている家族や移住を考えている家族の方に対し、木造二階建・4DKの電化住宅を福浦地区に建設し、将来的には入居された方に払い下げ、定住の促進を図るというものです。
原発反対を本気で考える人達は、安全な都市部から声を出すのではなく、こういった制度を利用して、現地の人達と「共に」考えていくというのは一つの方法だと思います。
住むことで、初めて見えてくることもたくさんあります。
もっとも、この事業の元のお金が、原発の交付金から出ているのは皮肉な話ではありますが…。
あと、これはあまり勧めたくない「裏技」ですが、現地に住民票を移して3ヶ月居住すると選挙権が得られます。
現在、上関町でも原発反対派は4割ほどいます。
それと合わせると、600~700人も反対派が住めば、現状の原発に対する賛成と反対が逆転するという現象が生じます。
ただし、
・移住者は町民に受け入れられないことは覚悟した上で
・それでも対話をあきらめず、粘り強く話し合うこと
・いったん、原発「賛否」の価値観を捨てて、幅広く現地の良いところも悪いところも見ること
・選挙後も住み続け、労働力になること
・現地に貢献すること
これらは絶対条件であり、必要最低限のマナーだと考えます。
それがなければ、移住しても迷惑なだけです。
実際に、某宗教団体を母体にしたとある政党は住民票を3ヶ月移して、選挙が終わると同時に住民票を引き上げることをしているという話はよく聞きますが、それと同じ汚いやり口になってしまうということは、強調しても強調しすぎることはないでしょう。
○上関町を訪れた人は、上関町の生活も意識的に見てみる:
これだけなら、ハードルはずっと低くなると思います。
全国から、「反原発」で上関町を訪れる人はたくさんいますが、上関町の人々と交流することはおろか、彼らの生活をまったく見もしないで、騒ぐだけ騒いで帰ってしまうことは非常に残念です。
いわば、「木を見て森を見ず」な状況なわけです。
上関町の自然について書かれた、いわゆる「反原発派」によるブログはたまに見かけますが、そこに地域の人達の暮らしについて書かれた文章を見かけることは、まったくと言っていいほど皆無なのです。
どんなに豊かな自然や綺麗な海があっても、それだけでは生きていけません。
それどころか、むき出しの自然は、人間にとって大きな脅威となって襲いかかることの方が多いのです。
ともかく、現地を訪れた人達は、どういう理由で訪れたのであれ、原発だけに視野狭窄するのではなく、上関町民の生活などに関心を持って先入観をなるべく持たずに見ることをして欲しいと願います。
抽象的な「反原発」よりも、原発を必要としなくても暮らせるような、人間らしい暮らしを取りもどすことへの協力を、現地を訪れた人達には考えて欲しいと切望します。
それがなければ、「反原発」を掲げることは、ヒューマニズムにもとる、ただのクレイマーでしかないと考えます。
○過疎地に対しての支援制度を利用する:
実は過疎地には、支援制度が存在します。
それは、『過疎地自立対策特別措置法』といいます。
産業の振興、生活環境の整備、高齢者の保健及び福祉の向上及び増進、医療の確保、教育の振興、集落の整備などを支援するお金が公費ででます。
28年前に、上関に原発案が持ち上がった段階ではその制度があったかどうか、また、上関町が条件にあてはまったかどうかはわかりません。
けれども、現在の上関町はその制度で規定する「過疎地」にあてはまります。(※山口県の公式ホームページで確認済みです。)
原発の交付金があったせいかわかりませんが、上関町はまだその制度を一度も利用していないようです。
最新版の『山口県過疎地域自立促進計画について』のPDFは以下のアドレスになります。
http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a123003/kaso/hosin-keikaku/apd1_3_2011020117163804.pdf
この制度を使えば、原発の交付金ほどのお金は入らなくとも、最低限の現状維持は可能かもしれません。
ただし、山口県は過疎地が上関町に限らず非常に多い県なので、どのくらいの支援費が入るのかは未知数という問題はあります。
それでも、一考には値するのではないかと考えます。
○NPOによる、共同体生活ネットワークサービスの利用:
上関町では、商店がないことにより、生鮮食品の入手も困難な家庭が多いと聞きます。
もしかすると、生協のような宅配でのサービスもないのかもしれません。
このような分野を、なるべく費用の負担をサービス受益者に負わせずに行うNPOも存在します(もちろん、無償とはいきませんが)。
こういった、NPOを活用して地域の共同体のあり方を作り直してみるという方法も一案だと考えます。
実際、過疎地の自立支援を専門にするNPOもあります。
現在、上関町では、細々と行われている農業や漁業についても、農協や漁協がきちんと機能していないという話も聞きます。
流通ルートがないから、産業が先細るのです。
こういった、販路をNPOを通じて開拓していくことも、地域の自立に向けた取り組みとして意義のあることではないかと考えます。
○「エンパワメント」という概念:
エンパワメントとは、直訳すると「力をつける」ということですが、もっと正確にいうと「自分自身の力で問題や課題を解決していくことができる社会的技術や能力を獲得すること」になります。
援助・被援助ではない、第3の道です。
この「エンパワメント」という概念を用いた福祉問題へのアプローチでは、当事者たち自身がそのおかれた状況に気づき、問題を自覚し、自分たちの生活をコントロールしたり、改善したりする力をつけることが目指されます。
実際、この概念は社会的マイノリティや少数民族、女性、障がい者の自立に関する考え方のベースとして使われています。
力(Power)をつけること、ないし力を獲得すること。
社会的・経済的な力をもたない貧しい人々や女性など、制度化された政治的・経済的過程に参加できず、人間開発の過程から排除され、力を奪われている(Disempowered)人たちが、自らの自己決定能力といった心理的な力や、社会的・政治的・法的な力を獲得する(自己をエンパワーする=self-empowerment)こと。
1970年代半ば以降、国連や国際会議の場で、「オルタナティブな開発」が唱えられ、「開発と女性」「持続可能な開発」、等が論じられる中で、貧困からの脱出や開発途上国の女性の「基本的ニーズ」に答えるための、環境・福祉優先型開発の必要が提起されるようになりました。
そうした議論の中で強調され、広まってきたのが、「エンパワーメント」の概念です。
交付金依存の生活では、自立ができなくなります。
そこからの脱却を考えていく上で、外せない概念だと考えます。
また、この概念を実際の生活に当てはめて実践していくには、先ほど挙げたような、過疎地支援を専門にしているNPOの協力を仰ぎながら、しっかりとしたロードマップ(工程表)を作成し、住民合意の元で行われる必要があります。
○外部人材の受け入れと「山村留学」:
先に挙げた、「Iターン」の話とも絡んできますが、過疎地でのIターンや外部人材の受け入れが成功している地域があります。
例えば、島根県隠岐島の海士(あま)町。
『なぜか「勝ち組」若者が移住してくる離島 5年半で230人の新規定住者獲得~島根県・海士町』
もちろん、地域的条件が同じではないですから、そのまま取り入れられない部分は多々あるでしょう。
それでも、参考になりそうな部分も多くあります。
例えば、2010年4月からスタートした「島留学制度」。
寮費を町が全額補助する学生寮を用意して、全国から学生を募集する。特色ある教育を打ち出すため、「地域創造」と「特別進学」の2コースを新設しています。
地域創造コースは、「将来、家業を継ぎたい」「地元の町を元気にする仕事をしたい」「いつか村長になる」など、地域社会で自立・活躍できる人材育成を目指すものです。
豊かな地域資源を活かした独自のプログラムや自然体験を通じて、主体性・想像力・コミュニケーション力を磨くことを目指しています。
特別進学コースは、大手予備校がない島の生徒でも難関大学を突破できる学力をつけるためのカリキュラムを用意し、少人数の徹底指導に加えて、島外から「進学のプロ」を招いた公営塾まで設置することを売りにしています。
このようにして、外部からの若い人材の確保、そして、地元で育った人が地元で仕事を創出する『人の自給自足』の流れを作り出そうとしています。
こういった離島での、子どもたちの受け入れは沖縄県などでもよく見られます。
例えば、久高島での「山村留学」。
久高島は他の多くの離島や僻地と同じように近年人口が減少し、学校も超小規模校となっています。
しかし、過疎や小規模校と言うハンディを逆手にとって、沖縄のこのような島だからこそできる活動があるということを「活動趣旨」で述べています。
全国の不登校児童生徒や、親が養育しにくくなった子どもたちをこういった地で受け入れ育て、やがては地域に貢献する人材に育てようと、地域ぐるみ島ぐるみで取り組んでいると聞きます。
このようなことは、沖縄では鳩間島や渡嘉敷島でも行っています。
鳩間島は、ドラマ『瑠璃の島』でもその様子が有名になりました。
かつて過疎化により島の小中学校が廃校の危機に直面したことから、島の人が「里親」となって島外からの児童を里子として受け入れる「海浜留学」を実施しているのです。
このような取り組みは、上関町などの過疎地域でも行うことができるのではないでしょうか?
将来の人材育成のためにも!
以上、様々なことを述べてきましたが、簡単な解決策はありません。
だから、どうしても、歯切れの悪さ、後味の苦さは残ります。
それでも、そういった諸々を受け止めつつ「共に生きて」いくことを志向したいです。
これら過疎地の人権、生活の確保が達成できたとき、初めて大きな声で「原発は必要ない、いらない!」とやっと言えるのだと思うのです。
Posted by よーかい at 04:17│Comments(8)
│一日の雑感。
この記事へのコメント
取材記:4までを拝読して、ご苦労さんでした!
小生は上関町を故郷とする現住人です。年齢は70歳、Uタウン組、
当論文で上関町を幅広い、客観的、具体的視野で見て頂いただき分析したのは貴殿が初めてでしょう、当地には反対派、推進派で優れた方々は多くいますが、少し発展的、改革的なことを提案するならば頭を叩かれる!既存意識の強い人間性、いわゆる「俺が大将」「島国根性」がはびこっています(両派を問わず)。最近、私もあきらめムードでおりましたが何が上関町の活性化のために取組みたくなりました(刺激されました)。
既に70歳、体力も衰えていますが考えることは若い者に負けないつもりです。もう一分張りしてみますか!
タイトルに「沖縄で小学校の先生になる!」と有りますが、中学校より小学校の方がいいですね!鉄は赤い内に叩かないと!人間も小さな内に教育しないと立派な人格は育たない!
教員試験頑張って下さい!当地の「賀茂神社」にお祈りしておきます。
小生は上関町を故郷とする現住人です。年齢は70歳、Uタウン組、
当論文で上関町を幅広い、客観的、具体的視野で見て頂いただき分析したのは貴殿が初めてでしょう、当地には反対派、推進派で優れた方々は多くいますが、少し発展的、改革的なことを提案するならば頭を叩かれる!既存意識の強い人間性、いわゆる「俺が大将」「島国根性」がはびこっています(両派を問わず)。最近、私もあきらめムードでおりましたが何が上関町の活性化のために取組みたくなりました(刺激されました)。
既に70歳、体力も衰えていますが考えることは若い者に負けないつもりです。もう一分張りしてみますか!
タイトルに「沖縄で小学校の先生になる!」と有りますが、中学校より小学校の方がいいですね!鉄は赤い内に叩かないと!人間も小さな内に教育しないと立派な人格は育たない!
教員試験頑張って下さい!当地の「賀茂神社」にお祈りしておきます。
Posted by 山本 at 2011年04月22日 10:21
>山本さん
こんばんは。
コメントどうもありがとうございます。
>小生は上関町を故郷とする現住人です。
そうでしたか…!∑( ̄□ ̄;)
この全4回の連載自体、薄氷を踏むような思いで書いていましたが、現地の上関町の方が読まれていたと知って、改めて滝汗ものです。
この連載記事は、下手をすると多くの人の人権などに関わったり、あるいはたくさんの人を傷つけうる可能性もあっただけに、「こんなこと書いていいのかなぁ…自分自身の力量を越えてはいないかなぁ…」と常に自問自答しながら書いていました。
>当論文で上関町を幅広い、客観的、具体的視野で見て頂いただき分析したのは貴殿が初めてでしょう
>最近、私もあきらめムードでおりましたが何が上関町の活性化のために取組みたくなりました(刺激されました)。
本当に、本当に、ありがたいお言葉です!
どうもありがとうございます!!(*´▽`*)
少しでも、そのように感じていただけたのなら、書いたかいがありました。
書いている間、そして書き終えてからもしばらく、緊張が身体から張り付いていた感覚だったので、ほっとしたのもあり、涙がでそうです。
>既に70歳、体力も衰えていますが考えることは若い者に負けないつもりです。もう一分張りしてみますか!
はい♪
こちらにも、協力できることがあれば、なんなりとお申し付けください。
微力でも、力になりたいです。
>教員試験頑張って下さい!当地の「賀茂神社」にお祈りしておきます。
ありがとうございます!!!
試験まであと約2ヶ月半。
全力であたりたいと思います!
こんばんは。
コメントどうもありがとうございます。
>小生は上関町を故郷とする現住人です。
そうでしたか…!∑( ̄□ ̄;)
この全4回の連載自体、薄氷を踏むような思いで書いていましたが、現地の上関町の方が読まれていたと知って、改めて滝汗ものです。
この連載記事は、下手をすると多くの人の人権などに関わったり、あるいはたくさんの人を傷つけうる可能性もあっただけに、「こんなこと書いていいのかなぁ…自分自身の力量を越えてはいないかなぁ…」と常に自問自答しながら書いていました。
>当論文で上関町を幅広い、客観的、具体的視野で見て頂いただき分析したのは貴殿が初めてでしょう
>最近、私もあきらめムードでおりましたが何が上関町の活性化のために取組みたくなりました(刺激されました)。
本当に、本当に、ありがたいお言葉です!
どうもありがとうございます!!(*´▽`*)
少しでも、そのように感じていただけたのなら、書いたかいがありました。
書いている間、そして書き終えてからもしばらく、緊張が身体から張り付いていた感覚だったので、ほっとしたのもあり、涙がでそうです。
>既に70歳、体力も衰えていますが考えることは若い者に負けないつもりです。もう一分張りしてみますか!
はい♪
こちらにも、協力できることがあれば、なんなりとお申し付けください。
微力でも、力になりたいです。
>教員試験頑張って下さい!当地の「賀茂神社」にお祈りしておきます。
ありがとうございます!!!
試験まであと約2ヶ月半。
全力であたりたいと思います!
Posted by よーかい at 2011年04月24日 02:15
完結するのを楽しみに読んでいました。
【いかなる状況であれ、立場の弱いものたちの生活や人権はなんとしても守られなくてはならない】
まったくそう思います。
九州でホームレスの自立支援ボランティアをやっています。
野宿者の中にも、原発労働で放射線管理を改ざんされ、それでも「高給だし履歴書いらないし」で(選べず)従事して、発病、亡くなった方も何人もおられます。
原発と経済は身近な問題でした。
限界集落の悲壮さは、上関だけのことではないですが、原発受け入れを町が決めたので出て行った(そこでの暮らしを諦めた)方もいます。
難しい問題ですが、そこに住んでいる方々が(金銭的な意味を超えて)豊かに暮らせたら・・・と願ってます。
概ね記事には賛同するところが多いのですが、「Ustreamやツイッターで上関原発についての話題」がよく見られるようになったのは、本当にここ最近のことです。
「祝島ばっかり」と思われたかも知れませんが、そこには歴史があります。
【立場の弱いもの】が、30年近い無償の「訴え」で、やっと、やっと声を世間に聴いてもらえるようになったのです。
「無関心」と書かれていましたが、祝島の人達(それを応援する人達も)は、推進せざるを得なかった上関町民のことはとても気にかけながら反対運動をやっています。もともと親戚であり友人だったのです。「何が彼らを引き裂いたのか」。とてもつらい思いを抱えています。
ネットでの発信は、その思いまで含める余裕もない「必死なひとこと」だったかもしれません。
上関に足を運ばれたように、串間でもいいですが、原子力発電に反対している【立場の弱いもの】の現場にも、行かれてみて欲しいと思いました。
けっして「脚光を浴びてる」わけでも「追い風が吹いてる」わけでも無いのです。
日本全体が「推し進めてきた」ことに対して反対するなら、「代替案を出してみろ」と封殺されてきた事実は、今も続いています。
【いかなる状況であれ、立場の弱いものたちの生活や人権はなんとしても守られなくてはならない】
まったくそう思います。
九州でホームレスの自立支援ボランティアをやっています。
野宿者の中にも、原発労働で放射線管理を改ざんされ、それでも「高給だし履歴書いらないし」で(選べず)従事して、発病、亡くなった方も何人もおられます。
原発と経済は身近な問題でした。
限界集落の悲壮さは、上関だけのことではないですが、原発受け入れを町が決めたので出て行った(そこでの暮らしを諦めた)方もいます。
難しい問題ですが、そこに住んでいる方々が(金銭的な意味を超えて)豊かに暮らせたら・・・と願ってます。
概ね記事には賛同するところが多いのですが、「Ustreamやツイッターで上関原発についての話題」がよく見られるようになったのは、本当にここ最近のことです。
「祝島ばっかり」と思われたかも知れませんが、そこには歴史があります。
【立場の弱いもの】が、30年近い無償の「訴え」で、やっと、やっと声を世間に聴いてもらえるようになったのです。
「無関心」と書かれていましたが、祝島の人達(それを応援する人達も)は、推進せざるを得なかった上関町民のことはとても気にかけながら反対運動をやっています。もともと親戚であり友人だったのです。「何が彼らを引き裂いたのか」。とてもつらい思いを抱えています。
ネットでの発信は、その思いまで含める余裕もない「必死なひとこと」だったかもしれません。
上関に足を運ばれたように、串間でもいいですが、原子力発電に反対している【立場の弱いもの】の現場にも、行かれてみて欲しいと思いました。
けっして「脚光を浴びてる」わけでも「追い風が吹いてる」わけでも無いのです。
日本全体が「推し進めてきた」ことに対して反対するなら、「代替案を出してみろ」と封殺されてきた事実は、今も続いています。
Posted by tanise at 2011年04月24日 16:21
>tanise さん
はじめまして。
こんばんは。
コメントどうもありがとうございます。
> 完結するのを楽しみに読んでいました。
どうもありがとうございます(*´▽`*)
>「Ustreamやツイッターで上関原発についての話題」がよく見られるようになったのは、本当にここ最近のことです。
「祝島ばっかり」と思われたかも知れませんが、そこには歴史があります。
そうですね。
たしかに、おっしゃる通りだと思います。
>上関に足を運ばれたように、串間でもいいですが、原子力発電に反対している【立場の弱いもの】の現場にも、行かれてみて欲しいと思いました。
はい。
ぜひそうしたいと思います。
社会人になってから障がい者関係の仕事を長年していることや、大学時代に横浜の寿町(日本の三大スラムのひとつ)やオーバーステイの外国人労働者のことについてフィールドワークをしたりしたこと、また自分自身の家庭環境などから、人権問題には全般的に関心があります。
正直、外部の人間が首をつっこんでいい問題だろうか?と自問自答することも多いですが、自分にとっては「人ごと」ではないのです。
>日本全体が「推し進めてきた」ことに対して反対するなら、「代替案を出してみろ」と封殺されてきた事実は、今も続いています。
たしかに。
この件についても、このブログを書いたから終わりではなく、まだまだ勉強が必要ですし、今後も継続して注視し、できうる範囲で最大限関わっていきたいと思っています。
はじめまして。
こんばんは。
コメントどうもありがとうございます。
> 完結するのを楽しみに読んでいました。
どうもありがとうございます(*´▽`*)
>「Ustreamやツイッターで上関原発についての話題」がよく見られるようになったのは、本当にここ最近のことです。
「祝島ばっかり」と思われたかも知れませんが、そこには歴史があります。
そうですね。
たしかに、おっしゃる通りだと思います。
>上関に足を運ばれたように、串間でもいいですが、原子力発電に反対している【立場の弱いもの】の現場にも、行かれてみて欲しいと思いました。
はい。
ぜひそうしたいと思います。
社会人になってから障がい者関係の仕事を長年していることや、大学時代に横浜の寿町(日本の三大スラムのひとつ)やオーバーステイの外国人労働者のことについてフィールドワークをしたりしたこと、また自分自身の家庭環境などから、人権問題には全般的に関心があります。
正直、外部の人間が首をつっこんでいい問題だろうか?と自問自答することも多いですが、自分にとっては「人ごと」ではないのです。
>日本全体が「推し進めてきた」ことに対して反対するなら、「代替案を出してみろ」と封殺されてきた事実は、今も続いています。
たしかに。
この件についても、このブログを書いたから終わりではなく、まだまだ勉強が必要ですし、今後も継続して注視し、できうる範囲で最大限関わっていきたいと思っています。
Posted by よーかい at 2011年04月25日 03:12
はじめまして。
ボクはツィッターからフォロァーさんの紹介で
ブログを知り、取材記4を拝見させていただきました。
感想としては力作、共感できる部分が多く、
ボクの今後の考えの参考にさせてもらった部分が多かったです。
ボクも今回、震災からの政府、東電の対応に疑問を持ち、
自分なりに原発の事を考え、調べていくうちに
原発立地にある過疎化の問題は避けて通れないモノである
との考えを持ちました。
よーかいさんもご存知だと思いますが、原発は中曽根政権からの
国策によって始められたエネルギー政策であり、高度経済成長、
今の日本を経済の礎を築き、
ボク達も豊かさを享受されてきた産物であります。
しかし、同時に「過疎化されてきた土地の雇用状況や財政状況など関係ない」とある種の差別感情が同時進行で進んできた政策であるとボクは理解しています。
よーかいさんの「構造の問題である」との主張には
100パーセント同意します。
その意味で、ボクのツィッター上に流れる
「東電前行動!東電許すまじ!」
の意見には首をかしげる所も多々あります。
東電もある種被害者ではないか?と。
東電だけに批判を集中させる事は物事の本質を誤らせる危険がある、とボク個人的には考えています。
その他のよーかいさんの主張、提案も
ボク的に凄く興味深かったです。
私事で恐縮なのですが、ボクは今回 ↓
http://akaruimirainihon.blog55.fc2.com/blog-entry-1.html
を立ち上げました。
活動報告は
http://akaruimirainihon.blog55.fc2.com/blog-entry-3.html
なカンジです。
よーかいさんにお願いなのですが、是非、ボクのブログなり
アドレスの方によーかいさんのご意見を頂戴できないでしょうか?
その際、よーかいさんの活動なりブログの紹介をしていただいて
もちろん結構です。
お忙しい、もしくはボクの活動に賛同できない、
という事でしたら、今回の取材記 4 をボクのブログで
紹介させて頂きたいので、それだけでも了承頂ければ嬉しいです。
お忙しいとは思いますが、お返事、お待ちしております。
ヤマネヤスタカ
Twitter @yamaneyasutaka
e-mail akaruimirainihon@gmail.com
ボクはツィッターからフォロァーさんの紹介で
ブログを知り、取材記4を拝見させていただきました。
感想としては力作、共感できる部分が多く、
ボクの今後の考えの参考にさせてもらった部分が多かったです。
ボクも今回、震災からの政府、東電の対応に疑問を持ち、
自分なりに原発の事を考え、調べていくうちに
原発立地にある過疎化の問題は避けて通れないモノである
との考えを持ちました。
よーかいさんもご存知だと思いますが、原発は中曽根政権からの
国策によって始められたエネルギー政策であり、高度経済成長、
今の日本を経済の礎を築き、
ボク達も豊かさを享受されてきた産物であります。
しかし、同時に「過疎化されてきた土地の雇用状況や財政状況など関係ない」とある種の差別感情が同時進行で進んできた政策であるとボクは理解しています。
よーかいさんの「構造の問題である」との主張には
100パーセント同意します。
その意味で、ボクのツィッター上に流れる
「東電前行動!東電許すまじ!」
の意見には首をかしげる所も多々あります。
東電もある種被害者ではないか?と。
東電だけに批判を集中させる事は物事の本質を誤らせる危険がある、とボク個人的には考えています。
その他のよーかいさんの主張、提案も
ボク的に凄く興味深かったです。
私事で恐縮なのですが、ボクは今回 ↓
http://akaruimirainihon.blog55.fc2.com/blog-entry-1.html
を立ち上げました。
活動報告は
http://akaruimirainihon.blog55.fc2.com/blog-entry-3.html
なカンジです。
よーかいさんにお願いなのですが、是非、ボクのブログなり
アドレスの方によーかいさんのご意見を頂戴できないでしょうか?
その際、よーかいさんの活動なりブログの紹介をしていただいて
もちろん結構です。
お忙しい、もしくはボクの活動に賛同できない、
という事でしたら、今回の取材記 4 をボクのブログで
紹介させて頂きたいので、それだけでも了承頂ければ嬉しいです。
お忙しいとは思いますが、お返事、お待ちしております。
ヤマネヤスタカ
Twitter @yamaneyasutaka
e-mail akaruimirainihon@gmail.com
Posted by ヤマネヤスタカ at 2011年04月28日 18:53
>ヤマネヤスタカさん
はじめまして。
コメントどうもありがとうございます。
リンクとして貼ってあるブログの方もすべての記事を拝見させていただきました。
>東電もある種被害者ではないか?と。
うーん、「被害者」の定義についてもう少し詳しい解説が欲しいところです。
定義次第になるような気がします。
まあ、東電自体は「子会社」みたいなもので、「親会社」の経団連や経済産業省が「国策」として進めていく構図をどうにかしないといけないかなとは思います。
それでも、いわば「パシリ」的な存在であったとしても、社会的責任として、東電が無罪放免とはいかないだろうなとも思います。
>「東電前行動!東電許すまじ!」
>の意見には首をかしげる所も多々あります。
いろんな視点や方法があっていいのではないでしょうか?
デモは平和的なものでも、公安が参加者の顔写真を子細漏らさずバシャバシャと撮影したりしますし、けっこう大変な作業なのですよ。
自分自身は参加はしませんが、そういう行動を非難する気もありません。
暴力的手段や少数の者を差別するような方法はあってはならないと考えますが、それ以外はさまざまな試行錯誤はあってしかるべきだと考えます。
>お忙しい、もしくはボクの活動に賛同できない、
>という事でしたら、今回の取材記 4 をボクのブログで
>紹介させて頂きたいので、それだけでも了承頂ければ嬉しいです。
原文を改編しないのであれば、紹介していただくぶんには構いません。
はじめまして。
コメントどうもありがとうございます。
リンクとして貼ってあるブログの方もすべての記事を拝見させていただきました。
>東電もある種被害者ではないか?と。
うーん、「被害者」の定義についてもう少し詳しい解説が欲しいところです。
定義次第になるような気がします。
まあ、東電自体は「子会社」みたいなもので、「親会社」の経団連や経済産業省が「国策」として進めていく構図をどうにかしないといけないかなとは思います。
それでも、いわば「パシリ」的な存在であったとしても、社会的責任として、東電が無罪放免とはいかないだろうなとも思います。
>「東電前行動!東電許すまじ!」
>の意見には首をかしげる所も多々あります。
いろんな視点や方法があっていいのではないでしょうか?
デモは平和的なものでも、公安が参加者の顔写真を子細漏らさずバシャバシャと撮影したりしますし、けっこう大変な作業なのですよ。
自分自身は参加はしませんが、そういう行動を非難する気もありません。
暴力的手段や少数の者を差別するような方法はあってはならないと考えますが、それ以外はさまざまな試行錯誤はあってしかるべきだと考えます。
>お忙しい、もしくはボクの活動に賛同できない、
>という事でしたら、今回の取材記 4 をボクのブログで
>紹介させて頂きたいので、それだけでも了承頂ければ嬉しいです。
原文を改編しないのであれば、紹介していただくぶんには構いません。
Posted by よーかい at 2011年04月29日 02:08
はじめに
今回のコメントは以前頂いたコメントに対する返信であり
この場所に記入するのは不適切かな、と個人的には思います。
(ブログから、よーかいさんへメールを送ろうとしたのですが、
パスワードがわかりませんでした)
ので、ご確認頂ければ削除していただければ、と思います。
>うーん、「被害者」の定義についてもう少し詳しい解説が欲しいところです。
定義次第になるような気がします。
そうですね。ボクが言う「被害者」とは
例えば、青山繁晴とゆう総合経済政策学科客員教授が、
ニュースアンカーという番組の1コーナーで
福島第一原発の所長(吉田さんだったかな?)は
現場の被害を食い止めようと最大限の努力をしている。
今、福島で最も恐れている事態は福島第5.第6原発からの
被害が拡大する事。原因としては津波。
スマトラでは震度9近くの地震が起こった後、三ヶ月後に震度8クラスの地震が来た事実がある。
その事から吉田さんは政府に一刻も早い原発の設備強化の工事を政府に要請しているが、政府は書類がどうの、法律ではなんたら、と言っていっこうに工事に着手しようとしない。そうゆうのもあって、吉田さんは「やってらんねぇよ!」と発言したんだと思う。
たる内容の事がユーチューブでUPされていました。
(もう消されているのでうる覚えですが、言ってる事はこんな事だったと思います)
その他にも、現地で復興作業にあたっている作業員に対しての
待遇の悪さがボクのTL上で話題になっていましたが、
これも東電現場側はもっと手厚く待遇したい、と考えているが
政府側の意向を受けて東電がOKできないのではないかな?
と思っています。
(これは情報源はありません。ボク個人的に思っている事です)
もちろん、青山さんの話が事実で、作業員に対しての憶測が
その通りだったとしても、今まで「絶対に安心」と推進してきた原発が今回の事故の補償を税金で賄ってもらおうとしている民間企業の社員にボーナスが出るって所で100パーセントアウトで、そこは糾弾されるべきだし、東電前、抗議行動に意味は無い、とは言いません。
が、「東電前、東電許すまじ」 と声を挙げるてる人の中で
原発がある事で生活している人達の事を一緒に考えている人がどれだけいるのかなぁ、という事がボクにとって引っ掛かってので、あのように記入させて頂きました。
>原文を改編しないのであれば、紹介していただくぶんには構いません。
もちろん、原文を改編するつもりはありません。
機会を見てボクのブログにUPさせて頂きたいと思っています。
ブログのUP了承、ありがとうございました。
ヤマネヤスタカ
今回のコメントは以前頂いたコメントに対する返信であり
この場所に記入するのは不適切かな、と個人的には思います。
(ブログから、よーかいさんへメールを送ろうとしたのですが、
パスワードがわかりませんでした)
ので、ご確認頂ければ削除していただければ、と思います。
>うーん、「被害者」の定義についてもう少し詳しい解説が欲しいところです。
定義次第になるような気がします。
そうですね。ボクが言う「被害者」とは
例えば、青山繁晴とゆう総合経済政策学科客員教授が、
ニュースアンカーという番組の1コーナーで
福島第一原発の所長(吉田さんだったかな?)は
現場の被害を食い止めようと最大限の努力をしている。
今、福島で最も恐れている事態は福島第5.第6原発からの
被害が拡大する事。原因としては津波。
スマトラでは震度9近くの地震が起こった後、三ヶ月後に震度8クラスの地震が来た事実がある。
その事から吉田さんは政府に一刻も早い原発の設備強化の工事を政府に要請しているが、政府は書類がどうの、法律ではなんたら、と言っていっこうに工事に着手しようとしない。そうゆうのもあって、吉田さんは「やってらんねぇよ!」と発言したんだと思う。
たる内容の事がユーチューブでUPされていました。
(もう消されているのでうる覚えですが、言ってる事はこんな事だったと思います)
その他にも、現地で復興作業にあたっている作業員に対しての
待遇の悪さがボクのTL上で話題になっていましたが、
これも東電現場側はもっと手厚く待遇したい、と考えているが
政府側の意向を受けて東電がOKできないのではないかな?
と思っています。
(これは情報源はありません。ボク個人的に思っている事です)
もちろん、青山さんの話が事実で、作業員に対しての憶測が
その通りだったとしても、今まで「絶対に安心」と推進してきた原発が今回の事故の補償を税金で賄ってもらおうとしている民間企業の社員にボーナスが出るって所で100パーセントアウトで、そこは糾弾されるべきだし、東電前、抗議行動に意味は無い、とは言いません。
が、「東電前、東電許すまじ」 と声を挙げるてる人の中で
原発がある事で生活している人達の事を一緒に考えている人がどれだけいるのかなぁ、という事がボクにとって引っ掛かってので、あのように記入させて頂きました。
>原文を改編しないのであれば、紹介していただくぶんには構いません。
もちろん、原文を改編するつもりはありません。
機会を見てボクのブログにUPさせて頂きたいと思っています。
ブログのUP了承、ありがとうございました。
ヤマネヤスタカ
Posted by ヤマネヤスタカ at 2011年04月29日 16:05
>ヤマネヤスタカさん
連休中不在にしていたため、返信遅くなりましたm(_ _)m
すみません。
コメントどうもありがとうございます。
>福島第一原発の所長(吉田さんだったかな?)は
>現場の被害を食い止めようと最大限の努力をしている。
そうですね。
しかし、これは吉田所長個人の頑張りであって、東電のバックアップはほとんど得られていない模様です。
>現地で復興作業にあたっている作業員に対しての
>待遇の悪さがボクのTL上で話題になっていましたが、
>これも東電現場側はもっと手厚く待遇したい、と考えているが
>政府側の意向を受けて東電がOKできないのではないかな?
>と思っています。
うーん?
これは、様々なニュースを検証してみても、とてもそうは思えませんでした。
命がけで原発作業にあたっている作業員のほぼすべては東電の正規職員ではなく、下請け企業の職員です。
毎日雑魚寝、そしてやっと弁当の支給が決まりましたが、それまで食事はカンパンでした。
一方、東電はヤマネさんのコメントにも少しありますように、役員のボーナスは5割カットでも2000万円以上です。
東電職員の平均給与は一般企業よりもはるかに高く、約800万円だとも聞きます。
2割削減でも、640万円がでるわけです。
一方、下請け企業の方は、もともと月18万円台から23万円台の給料、ボーナスなしでした。
今は危険手当が付くとしても、待遇改善を積極的に行おうという姿勢は観られません。
「東電を潰さない政府案では国民負担10兆円、解体すれば0.9兆円で済む」
という話もありますが、もっと詳しく検証され、東電、政府双方がきちんと説明責任を果たす必要があると思います。
http://gendai.ismedia.jp/articles/-/2761?page=2
>「東電前、東電許すまじ」 と声を挙げるてる人の中で
>原発がある事で生活している人達の事を一緒に考えている人がどれだけいるのかなぁ、という事がボクにとって引っ掛かってので
それ以上に、デモが行われていることを一切報道しないメディアのあり方など、おかしな点はたくさんあるように感じます。
浜岡原発停止については、当然の措置だとは思いますが、現地の人達の生活や雇用をどうするのかについて政府はきちんとした説明をしていません。
デモのあり方よりも、そういった政府の対応や説明責任こそ糾弾されるべきだと考えます。
連休中不在にしていたため、返信遅くなりましたm(_ _)m
すみません。
コメントどうもありがとうございます。
>福島第一原発の所長(吉田さんだったかな?)は
>現場の被害を食い止めようと最大限の努力をしている。
そうですね。
しかし、これは吉田所長個人の頑張りであって、東電のバックアップはほとんど得られていない模様です。
>現地で復興作業にあたっている作業員に対しての
>待遇の悪さがボクのTL上で話題になっていましたが、
>これも東電現場側はもっと手厚く待遇したい、と考えているが
>政府側の意向を受けて東電がOKできないのではないかな?
>と思っています。
うーん?
これは、様々なニュースを検証してみても、とてもそうは思えませんでした。
命がけで原発作業にあたっている作業員のほぼすべては東電の正規職員ではなく、下請け企業の職員です。
毎日雑魚寝、そしてやっと弁当の支給が決まりましたが、それまで食事はカンパンでした。
一方、東電はヤマネさんのコメントにも少しありますように、役員のボーナスは5割カットでも2000万円以上です。
東電職員の平均給与は一般企業よりもはるかに高く、約800万円だとも聞きます。
2割削減でも、640万円がでるわけです。
一方、下請け企業の方は、もともと月18万円台から23万円台の給料、ボーナスなしでした。
今は危険手当が付くとしても、待遇改善を積極的に行おうという姿勢は観られません。
「東電を潰さない政府案では国民負担10兆円、解体すれば0.9兆円で済む」
という話もありますが、もっと詳しく検証され、東電、政府双方がきちんと説明責任を果たす必要があると思います。
http://gendai.ismedia.jp/articles/-/2761?page=2
>「東電前、東電許すまじ」 と声を挙げるてる人の中で
>原発がある事で生活している人達の事を一緒に考えている人がどれだけいるのかなぁ、という事がボクにとって引っ掛かってので
それ以上に、デモが行われていることを一切報道しないメディアのあり方など、おかしな点はたくさんあるように感じます。
浜岡原発停止については、当然の措置だとは思いますが、現地の人達の生活や雇用をどうするのかについて政府はきちんとした説明をしていません。
デモのあり方よりも、そういった政府の対応や説明責任こそ糾弾されるべきだと考えます。
Posted by よーかい at 2011年05月07日 17:07